空の旅は時々退屈だ、とリルムは思う。初めて飛空艇に乗った時には、こんなことを考える日が来るなんて想像もつかなかったけど、まったく慣れとは恐ろしいものだ。誰かにちょっかい出して遊ぼうと考えながらファルコンの広間に入って行くと、そこにいたのはソファに座ってうつむきかげんになっているティナ一人だった。
「何してるの?」
その背後から肩越しにのぞきこむ。膝の上に置いた自分の手をじっと見つめていたティナが、はじかれたように顔を上げた。
「わ、リルム!」
「あ、それって……」
ティナの視線の先、手の中にあるものを見て、リルムは言葉を止めた。
魔石。ティナの父、マディンの魔石だった。ティナが少しばつが悪そうに笑った。
「借りてきちゃった。まずかったかしら」
「そんなことないと思うけど。ティナの、お父さんの魔石……だよね、それ」
「うん。……時々、こうやってそばにいたくなるの。なぜだかわからないけど、ほっとするみたい」
ティナはまた手の中に視線を戻した。嬉しそうだ、とリルムは思った。
「わたしね、自分にお父さんがいるなんて、思ってなかった。どんな人だろうなんて考えたこともなかったの。なのにわたしにはお父さんがいて、今こうやって一緒にいる。なんだか、不思議な感じ……」
その言葉を聞いて、リルムは小さくため息をついた。
「あたしのパパは……今頃、どうしてるのかな……」
「え?」
ティナが魔石から目を離し、リルムを見た。
「あたしにもパパがいたんだよ。……でも、まだ小さい頃に、パパはサマサを出て行っちゃった。それからずっと会ってなくて、もう顔も覚えてないんだ。どこかで会っても、あたしはパパだってわかんないだろうし、パパもあたしのことわかんないだろうな……それとも、わかっても何も言ってくれないかな……」
そこまで話して、リルムははっと我に返った。
「ご、ごめん。変な話して」
「え? なんで謝るの? 全然変じゃないよ」
「そう……? なら、いいんだけど」
「でも、リルム」
ティナが少し首をかしげた。
「リルムって、小さい頃には絵を描いてなかったの? お父さんの似顔絵とか……」
ぎくり、とリルムの表情がこわばる。それを見てティナが不思議そうな顔をした。
「……えっと、描いてなかったわけじゃ、ないんだけど」
「描いてたの? だったら……」
「あたし、まだちっちゃかったもん。絵もヘタだったんだよ」
「嘘ー。今あんなにうまいのに」
ティナが無邪気に笑った。絵が下手なリルム、というのを想像できないようだった。
「あたしだってヘタな頃はあったの。今見るとほんとに恥ずかしいよ」
「えー? 今よりはうまくないってだけでしょ?」
どこまでもリルムの画才を過信しているティナに、それを見せてみたいと思ったのはなぜなのか。
「……見る?」
「わあ、ファルコンにあるの? 見たい! 見せて!」
目を輝かせたティナを前にして、リルムは自分の口からこぼれた一言を早くも後悔し始めていた。
ファルコンに来てからというもの、インターセプターは時折シャドウのそばから姿を消すようになった。賢い犬は、どうやらファルコンが主人にとって安全な場所だと見極め、常に護衛をする必要を感じなくなったらしい。しかし、飼い主としてはいつもそばにいるはずの犬が見当たらないとどうも落ちつかず、ついうろついて探してしまうようなことになる。
(飛空艇だからな……)
機械の中にでも巻き込まれたらどうなるのか。あの犬がそんなところに近づくはずはないと思ってはいても、少し不安になる。
「わあ! この人がリルムの?」
「あー、やっぱり見ないで! もう返してー!」
広間の方から、少女のはしゃいだような声が重なって聞こえてきて、シャドウはそちらに足を向けた。インターセプターはおそらくその足元にでも寝そべっているのだろうと思ったからだ。シャドウのパートナーである忠実な犬は、ファルコンのメンバーの中で一番年若い少女に妙になついていた。姿を確認したら部屋に戻ろうと考えながら広間に入ると、ティナが気づいて振り向いた。
「あ、シャドウ! ねえねえ、今リルムの絵を見せてもらってたの!」
「ちょ、ちょっとティナ!」
「この人、リルムのお父さんだって」
ティナはにこにこ笑いながら、手に持っていた画用紙をシャドウの方に向けた。
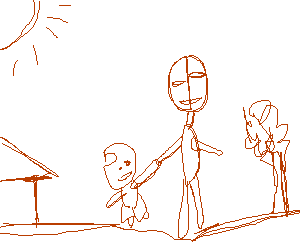
見たのはほんの一瞬だった。リルムがわあわあ言いながら画用紙の前に立ちふさがったからだ。
「見ないで! 見ないでってば! 忘れてー!」
しかしシャドウはすでに見てしまっていたし、目に焼きついたそれを忘れることもできそうになかった。自分の表情が隠れていることをこれほど感謝したのはいつ以来かと思う。
(……似て……いる)
しかも、どちらかというと今の自分に。あの村にいた頃の自分はこんな容姿ではなかったはずだ。子供の絵というのは皆このようなものなのか、それともリルムの画才が未来すら予知していたとでもいうのか。
(何を馬鹿な)
シャドウは呆然としている間に自分の頭に入りこんできた妙な考えを急いで追い出した。その目の前でリルムが真っ赤になってティナにくってかかっていた。
「やめてよ! か、勝手に見せたりしないで!」
ティナの方はリルムがなぜ怒っているのか理解できないという表情だ。
「でも……お父さんを探すなら、みんながこの似顔絵見た方がいいんじゃない?」
「探すなんて言ってないよ! 第一こんなのが手がかりになるわけないでしょ!」
叫んだ後、リルムは今度はシャドウの方を向いてキッと睨んだ。
「言っとくけど、これはあたしが3歳か4歳くらいの時に描いたんだからね!」
シャドウは興味ないというそぶりをして返事をしなかった。リルムにとってそれが一番ありがたい反応だろうということくらいは察することができる。なぜそんな昔に描いたものをティナに見せることになったのかは知らないが、この絵がリルムにとって相当恥ずかしいものであることは間違いない。スケッチという特殊能力を持ち、その筆ですべてを写し、すべてを生みだす彼女にとって、絵を描くというのは特別なことだ。そして同時に彼女はまだ子供でもある。大昔のものだと笑い飛ばせるほど、この絵を描いてから年月は経っていないのだ。
しかしティナにはそれが分かっていないようだった。そもそも、この絵を下手だとも認識していないらしい。首をかしげながら言う。
「すごく素敵な人じゃない。優しそうで……」
「どこが!?」
(どこがだ?)
リルムの大声とシャドウの内心の声が重なった。
「こんな手がかりがあれば、きっと大丈夫よ。いつかどこかで会った時、きっとお父さんだってわかるわ」
「無理!」
(無理だろう、それは)
再び重なる。これで分かったら奇跡だ。第一、今目の前にいてもまったく気づいていないという事実が、手がかりにならないことを証明している。
「やっぱりリルムはすごいね。そんなに小さい時から絵を描けたなんて」
「うぅ……」
リルムは赤くなったり青くなったりしていた。ティナは目をきらきらさせている。どうやら本気で言っているようだ。シャドウの脳裏に「誉めて伸ばす」という言葉が浮かんだ。ティナはモブリズでたくさんの子供たちの親がわりになっていたというが、さぞいい母親だったに違いない。しかし今の状況ではいい効果を与えているとは言い難く、リルムは顔から湯気を噴き出さんばかりにして叫んだ。
「もうやだ! ティナのバカっ!」
「あ、リルム!?」
リルムがばたばたと走って広間から出て行った。耐えられなくなったらしい。
「ど、どうして? わたし、何かリルムを傷つけるようなこと……」
ティナがおろおろとシャドウを振り返りながら言った。シャドウが何も答えずにいると、ティナはあわててリルムを追いかけ、広間を出て行った。
残ったのはシャドウと、テーブルの上の一枚の絵。
「やれやれ」
拾い上げて、改めて見直す。かすかに記憶にあるような気がした。きっと描き終えたリルムが父親にも見せたのだろう。
くーん、という鳴き声が聞こえた。顔を上げると、ティナが出ていった戸口から入ってくるインターセプターの姿があった。
遠慮がちなノックの音がした。誰なのかは気配でもう分かっている。
「開いている」
シャドウが言うと、扉がゆっくりと開いた。小さな体が室内にすべりこみ、後ろ手に扉を閉めた。
「……かくまって……ちょっとだけ」
泣きそうな顔をしているリルムに、シャドウは冷たく返した。
「連中はまだ探しているぞ。どうするつもりだ」
「ほとぼりが冷めるまででいいから。今出てくのはやだよ……」
広間から逃げ出したリルムを追ったティナは、あちこちの部屋に飛びこみ、血相を変えて「リルムを見なかった?」と尋ね回った。その結果、現在メンバーの大部分がリルムを探している状態だ。
「ほとぼりが冷めるも何も、お前が出ていかなければ探し続けるだろう」
「……もう少したったらさ、色男あたりが気をきかせて、『知らん顔していれば出てくるんじゃないか』なんて言ってくれると思うんだ」
「ここは飛空艇内だ。近づくと危険な場所もあるから連中は探し回ってる。気を利かせる奴などいるはずがない」
シャドウがそう言うと、リルムは呻くような声をあげながら椅子に腰かけ、頭をかかえた。
リルムにも本当はそのことが分かっているのだ。それでも恥ずかしくて出ていきたくないのだろう。あの絵を下手だと思っていないティナは、リルムがなぜ逃げ出したのかも分かっていない。会う者にいきさつをすべて話し、しかし幼少時の絵が下手だったという部分は抜けているから、聞く者はリルムが謎の行動をとったように受け取ってしまっている。
こんなことになるのなら、ティナに「その絵は本当に下手なのでリルムはそれを恥じているのだ」と言ってやればよかったかもしれない。シャドウは内心少々後悔していたが、今となってはもう遅い。
「やだやだやだー……」
リルムが弱々しく悲鳴をあげた。
「みんなの前であれを返されるなんてやだー」
「……ああ」
それを聞いてシャドウは立ち上がり、机の引き出しを開けた。
「これか?」
「……あ。え、えー!」
目の前に出されたものを、リルムはひったくるように取り上げた。
「な、なんで? なんでシャドウが持ってるの?」
「ティナがそれを置いてお前を追いかけていったからな。そのまま置いておくのもどうかと思……」
「ありがとう!」
我を忘れたかのようにリルムが叫んだ。
「ほんとにありがとう、シャドウ! あー! これで最悪の事態はまぬがれたよー」
絵を抱きしめ、大きく息をつく。そして絵を体から離してまじまじと見つめ、複雑な笑いを浮かべて言った。
「こんなの、天才リルム様の恥部だもん」
ならばなぜ、そんなものを飛空艇に持ち込んだのか。シャドウの内心の声が聞こえたかのように、リルムは顔を上げて言い訳じみた口調で言った。
「この前さ、サマサに寄ったでしょ? あの時に偶然見つけたの、これ」
「見つけたから持ってきたのか?」
リルムは困ったような顔になった。そしてもう一度絵を見て、困ったような顔のまま笑った。
「……あたしには、パパがいるの。今どこにいるかわからないし、顔も覚えてないけど、きっと生きてると思う。この絵はね……そのパパを描いた絵なんだよ。多分、パパを描いた絵は、この一枚しかない」
「…………」
「ファルコンでさ、世界のあちこち飛んで、いろんな街に降りて……それで、街の中歩いたりしてると、時々すごくあせるんだよね。もしかしたら、この中にパパがいるのかもしれない、すれ違ったのに気づかなかったのかもしれないって。それで、パパと会うチャンスは今日だけで、これを逃したら二度と会えないのかも、なんて思ったりしてさ」
また絵を見て笑う。けれどもその笑顔は、今度ははっきりと悲しそうだった。
「この絵が手がかりになるなんて、思ってないよ。だけど、パパの顔描いたのこれだけだからさ……そばに置いときたかったんだよ。お守りみたいなもんかなー」
シャドウは黙っていた。リルムが父親に会いたがっているなど、今まで聞いたことはなかった。娘を捨てて村を出て行った、顔も覚えていない父親に会いたいのか。会ってどうするつもりなのか。
「会いたいのか、父親に」
よけいなことは言わないつもりでいたが、ついその疑問が口をついた。
「うん……会いたい、かな。あたし、パパがいた頃のこと、あんまり覚えてないんだ。だからその頃のこと、聞かせてほしい」
「その頃? ……そんな絵を描いていた頃か」
リルムがむっとした顔でシャドウをにらみ、それから思い直したように笑った。
「そうだね。それもその頃のことに入るよね」
年に似合わない表情で、リルムはまた絵に見入った。今目の前にいる男がその頃のことを知っているなど、思いもよらないだろう。
その絵がどんなふうに描かれたものか、シャドウは知っている。絵を机の引き出しに入れる前にもう一度見直した時、まるで記憶をせき止めていた何かが壊れたようにいっぺんに思い出した。
あの家には、母親の絵も残っていただろうか、とふと思った。最初、リルムは母親の絵を描いていたのだ。
「ねえパパ、見て。ママの絵描いた!」
「なんだ、俺のはないのか?」
そう言うと、リルムは父親のリクエストが嬉しかったらしく、すぐさま椅子によじ登った。
「描くー。パパの絵も描く!」
少し高いテーブルに、持ち上げるように肘をのせて、真剣な顔で画用紙に向かう。横からのぞこうとすると、だめ! と隠された。
「できてのおたのしみ!」
得意げにそう言い放ち、あっち行っててなどと命令する。しばらくして絵が完成し、今度はパパこっち来てとわめく。
「見て! できたの!」
「ふーん、どれ」
「あら、じょうず」
母親にすかさずほめられ、リルムは顔中を笑顔にした。
「おいおい、髪の毛がないぞ」
「でも、パパだもん!」
父親がほめてくれなかったためか、すぐに不満げな顔になる。
「パパだよっ! パパ!」
「ああ、似てる似てる」
「これはねえ、パパがリルムと手つないでるところ!」
「そうだな。うまく描けてるよ」
「なかよしだから手をつないでるの!」
「うん」
「えへへへー」
リルムは嬉しそうに笑い、絵と同じように父親の手をつかまえた。両手で持ち、ぶらさがる。父親がリルムを抱き上げ、ゆらゆらとゆする。リルムはきゃっきゃっと高い声をたてて笑った。
そんな話を聞きたいのだろうか。たとえそうだとしても、話す機会が訪れることは決してない。
「さて」
リルムがふっきるように絵から目を離した。
「探してる皆さんのところに顔出してくるかなー? 気は進まないけどさ」
「早くすませた方がいいだろうな」
「うん……。あ、その絵、もうちょっとだけここに置いといてくれる? 後ですぐ取りに来るから」
「……ああ」
リルムは立ち上がり、己を鼓舞するように拳を軽く振った。扉を開け、一度振り返った。
「ありがとね、シャドウ」
扉が閉まった。その風圧で、テーブルの上の紙が揺れた。シャドウはそれをちらりと見て、すぐに目をそらした。
ここ数年は、サマサでの暮らしのことなど思い出すこともなかった。思い出したのは、この絵を見たせいだ。記憶の扉を勝手に開けられたかのように、眼前にあの頃の光景が浮かんできた。一つの記憶を足がかりに、次々と蘇ってくるあの頃の記憶。あたたかく、まぶしく、息が止まりそうになる。その感覚は恐怖によく似ていた。
インターセプターが不審そうにテーブルの上の絵の匂いをかいだ。かぎながら絵をじっと見ている。振り返ってシャドウに目をやり、また絵に目を戻した。見比べているようなその動きに、やっぱり似てるか、シャドウは苦笑してつぶやいた。